いつもお世話になっております、ルル区長です。
よく「公務員は退職金がたくさんもらえるから良いよね」と言われることがあります。

実際公務員として定年を迎えると退職金はいくら貰えるんでしょうか?
今回はそんな公務員の退職金制度について徹底解説していこうと思います!
公務員の退職金制度

公務員の退職金制度の基本的な考え方は、退職時の基本給(給料月額)×勤務年数に勤務年数に応じた補正率を乗じて計算するというものです。
また、役職によって「調整額」が加算されたりします。

意外とシンプルですよね!
勤務年数に応じた補正率は同じ年数勤務したとしても「定年を迎えて退職した場合」と「自己都合により退職した場合」で異なる点には注意が必要です。
また、公務員の退職金を算出する際には最終的に基本給と勤務期間で算出された額に「調整率」を乗じて最終的な金額が決定されます。

ちなみに現在の退職金における調整率は83.7%です。
それではここから一つずつ解説していきます!
定年を迎えて退職した場合の補正率
まずは「定年を迎えて退職した場合の退職金」について解説します。

これが世間一般に公務員の退職金が多いといわれるパターンのやつですね笑
注意しておきたいのは同じ定年でも「公務員になってから定年まで勤務した期間によって補正率が異なる」点です。
わかりやすい例で言うと、22歳新卒で入った人と35歳中途で入った人では退職金の補正率は異なるということです。
この区分についてそれぞれ見ていきましょう!
勤続年数が11年以上25年未満で定年退職した場合

まずは「勤続年数が11年以上25年未満で定年退職した場合」についてです。

定年が60歳とすると民間からの転職等で36歳になる年以降に入庁して11年以上勤務して定年を迎えた場合にこの補正率が適応されます!
勤続年数が11年以上25年未満で定年退職した場合の補正率を以下の表に示します。
| 勤務期間 | 1年あたり補正率 |
|---|---|
| 1年以上10年以下 | 125/100 |
| 11年以上15年以下 | 137.5/100 |
| 16年以上24年以下 | 200/100 |
勤続年数が25年以上で定年退職した場合
次に「勤続年数が25年以上で定年退職した場合」についてです。

定年が60歳とするとこの補正率が適応されるためには35歳になる年までに公務員になっていなければなりませんね!
勤続年数が25年以上で定年退職した場合の補正率を以下の表に示します。
| 勤務期間 | 1年あたり補正率 |
|---|---|
| 1年以上10年以下 | 150/100 |
| 11年以上25年以下 | 165/100 |
| 26年以上34年以下 | 180/100 |
| 35年以上 | 105/100 |
全体的に高い補正率でまとまっているのがわかると思います。
自己都合で退職した場合の補正率
次に「自己都合により退職した場合の退職金」について解説します。
想像がつくかと思いますが、「自己都合により退職した場合」は「定年を迎えて退職した場合」に比べて補正率は小さくなります。

この補正率は自己都合の理由によっても異なってきます!
自己都合の理由が「死亡・傷病」の場合
自己都合による退職する理由が「死亡・傷病」の場合の補正率を以下の表に示します。
| 勤務期間 | 1年あたり補正率 |
|---|---|
| 1年以上10年以下 | 100/100 |
| 11年以上15年以下 | 110/100 |
| 16年以上20年以下 | 160/100 |
| 21年以上25年以下 | 200/160 |
| 26年以上30年以下 | 160/100 |
| 31年以上 | 120/100 |
自己都合の理由が「死亡・傷病」以外の場合(転職等)
自己都合による退職する理由が「死亡・傷病以外」(転職等)の場合の補正率を以下の表に示します。
| 勤務期間 | 1年あたり補正率 |
|---|---|
| 1年以上10年以下 | 60/100 |
| 11年以上15年以下 | 80/100 |
| 16年以上20年以下 | 90/100 |

結構がっつり補正率が下がりましたね…
勤務期間が20年以上の補正率については自己都合理由が「死亡・傷病」の場合と同様になります。
長期勤続者に対する退職手当の額の計算の特例
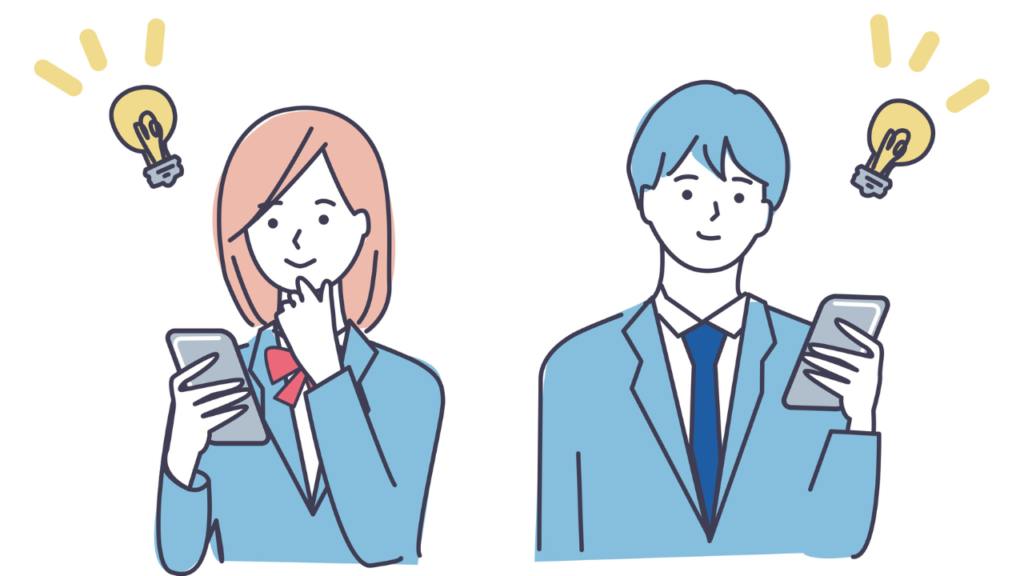
現在、公務員の退職金制度には条例等で特例が定められており、退職手当の算出に一部制限がかかっています。
特例による主な制限は以下の2点です。
- 勤務年数×勤務年数による補正率を乗じた合計に補正率(83.7/100)を乗じる
- 35年を超えて勤務しても退職手当算出時の勤務期間は35年で計算される

この内容の記載がある条文の中に「当分の間」とあるのでしばらくこの制限は変わらないと思います。
特例により現在の退職金支給月数の最大値は47.709カ月分になります
「長期勤続者に対する退職手当の額の計算の特例」を適応すると現在の公務員の退職金支給月数の最大値は47.709カ月になります。

公務員の退職金でよく見る数値ですよね!
この数値の算出方法について、35年勤務して定年退職した場合を考えてみます。
勤務年数が25年以上の場合の補正率を適応します。
10×1.5(1~10年目)+11×1.65(11~25年目)+14×1.8(26~34年目)+1×1.05(35年目)=57.00
これに特例による補正率83.7/100を乗じて
57.00×0.837=47.709
となります!

これが公務員の退職金が給料の47.709カ月分といわれる所以です。
退職手当の調整額

上記で算出した支給月数に加えて、公務員には各役職ごとの在籍期間に応じた調整額が加算されます。

在籍期間は月単位で上位の役職から数えて最大60カ月まで支給されます!
以下に、調整額についての表をまとめてみました。政令市の代表例として新潟市の区分分けもつけています!
| 区分 | 金額 | 役職(新潟市) |
|---|---|---|
| 第1号区分 | 65,000円 | 9級(理事級) |
| 第2号区分 | 59,550円 | 8級(部長級) |
| 第3号区分 | 54,150円 | 7級(部次長級) |
| 第4号区分 | 43,350円 | 6級(参事・課長級) |
| 第5号区分 | 32,500円 | 5級(副参事・課長補佐級) |
| 第6号区分 | 27,100円 | 4級(課長補佐・主幹級) |
| 第7号区分 | 21,700円 | 3級(係長・主査・副主査級) |
| 第8号区分 | 0円 | 第1~7号区分以外の職員 |
区分と金額については基本的にどの自治体でも同じです。ただし、各区分に対応する役職名は自治体によって異なるので注意してください。

他自治体について気になる方は自治体HPの例規集から「退職金手当支給条例」・「退職金手当支給条例施行規則」を調べてみてください!
大学卒業~定年まで勤務した場合の退職手当額

参考に、大学卒業後公務員に就職して定年まで働いた場合の退職金について計算してみようと思います。

今回は新潟市の職員の場合で計算していきます!
新潟市役所に22歳で就職し、60歳で定年を迎えたとすると勤務期間は38年間になります。
この場合、制度上の勤務期間は35年となり支給月数は47.709カ月分となります。
次に定年時の基本給(給料月額)の額を決定します
基本給については新潟市HPに掲載されている「令和6年職員の給与等に関する報告および勧告」の参考資料から定年時の級と号俸のボリュームゾーンから想定し6級73号俸(課長級)とします。

新潟市行政職員の6級73号俸の給料月額は412,700円です!
また、調整額について各区分ごとの在籍期間は以下の表のとおりとします。
| 区分(新潟市) | 金額 | 在籍期間 |
|---|---|---|
| 第4号区分(課長) | 43,350円 | 2年(24カ月) |
| 第5号区分(課長補佐) | 32,500円 | 3年(36カ月) |
| 第6号区分(課長補佐) | 27,100円 | 3年(36カ月) |
| 第7号区分(係長) | 21,700円 | 4年(48カ月) |
この場合、調整額の最大月数が60カ月なので上から第4号区分の24カ月、第5号区分の36カ月の計60カ月分が退職手当に加算されます。
以上の内容から退職手当額を算出すると、
{412,700(円)×47.709(月)}+{43,350(円)×24(月)+32,500(円)×36(月)}
=21,899,904円(少数以下切り捨て)

課長クラスで定年退職すると退職金はおおよそ2200万円ほど貰えそうですね!
ただし退職金ももちろん課税対象となっており、退職金控除がありますが手取りでは算出した額より少なくなる点に注意して下さいね!笑
以下に参考として新潟市の退職金に関する条例のリンクを貼っておきます!

退職金を計算するうえで便利なサイトがありましたのでそちらも紹介しておきます!
まとめ
ここまで、公務員の退職金制度について解説してきました!
まとめると、
- 公務員の退職手当は勤務年数に勤務年数に応じた補正率を乗じて計算される
- 上記に加えて役職ごとの調整額が最大60カ月分加算される
- 勤務年数による補正率は「定年退職」と「自己都合退職」の場合で異なる
- 特例により勤務年数により算出された額に補正率(83.7/100)がかかる
- 特例により退職手当算出時の勤務年数の最大値は35年になる
- 公務員の退職手当は最大で基本給の47.709カ月分(役職による調整額を除く)
こんな感じでしょうか!
この記事が公務員の制度について興味のある方の参考になったら嬉しいです。
これからも公務員に関する有益な情報を発信していきたいと思います!
それでは、失礼いたします。


